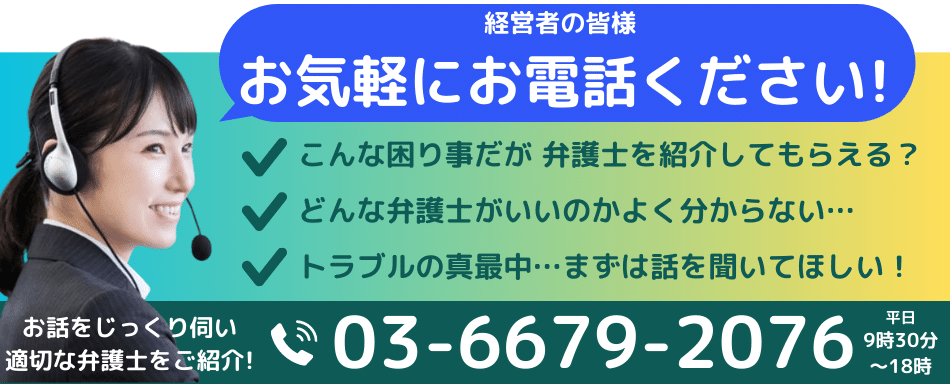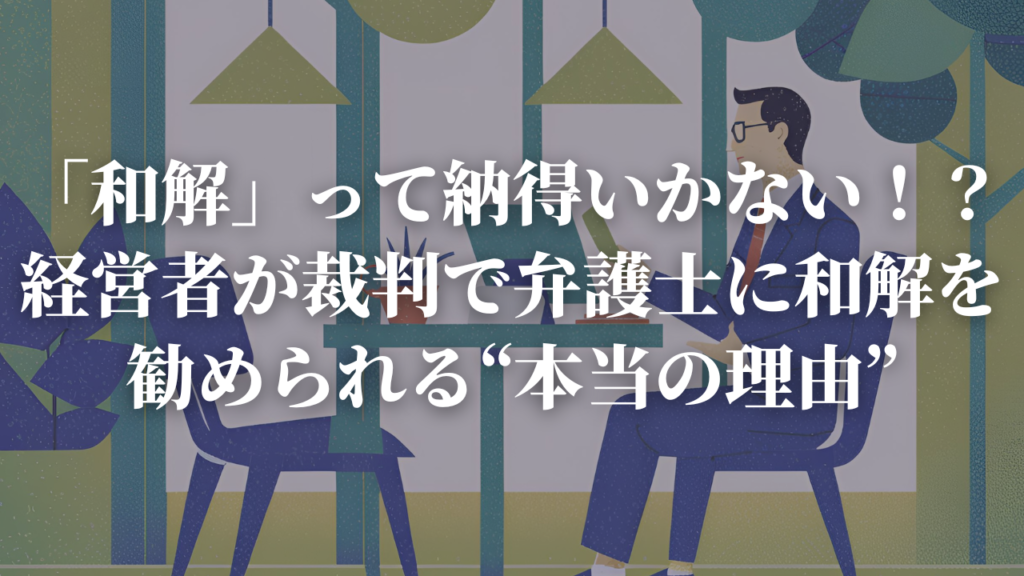
1.和解を勧められて、「納得いかない」と感じたことはありませんか?
裁判中に自社の弁護士から「和解を検討しませんか」と言われ、思わず納得がいかない気持ちになった――。
そんな経験をお持ちの経営者の方は少なくないと思います。
「和解」と聞くと、“妥協”や“敗北”のように感じる。
そして、「自社の主張の方が筋が通っている。きっと勝てるはずだ」と納得がいかない。
そうお考えの方は多いと思います。
とはいえ、実際の裁判の現場では、判決に至る前に和解で終結するケースの方が実は多いのです。
・なぜ弁護士は和解を勧めるのか?
・それはどのような背景や事業があるのか?
本記事では、弁護士の立場から「和解の意義」について、裁判実務の現実も交えて率直にお伝えます。
L.A.P.中小企業顧問弁護士の会、弁護士のE がお伝えします。

\和解を勧められたけど、納得できない…そんな方は、企業法務に詳しい弁護士から“セカンドオピニオン”をもらいませんか?/
2.裁判官が語った「争いが一つ減るということ」
多くの場合、裁判では、裁判官から和解を検討するよう勧奨があって、双方が和解を検討し、話がまとまれば和解によって紛争が終結することになります。
和解の意義を考えるにあたって、まず、和解を勧める裁判官の目線に立ってみましょう。
少し昔話をさせてください。
ご存知の通り裁判官は、裁判所で被告人に刑事事件の判決を言い渡したり、民事事件の勝ち負けを決めたりするお仕事です。
裁判官は判断を出す側ですから、弁護士や検察官とは異なり、「望んだ内容の判決がもらえた、もらえなかった」ですとか、「裁判に勝った、負けた」のような、わかりやすい結果が出ることがありません。
また裁判官は公務員ですので、弁護士のように、1年1年でお給料が大きく上下することもないと思います。
日々のお仕事の内容が「勝ち負け」や「手取り」というかたちで目に見えない職業の方は、何をモチベーションにしているのでしょうか?
気になった私は、司法修習生の時分に、裁判官に直接訊いてみたことがあります。
返ってきた答えは、
「何というか……自分のやったことで、世の中の争いが一つ減るというのは、いいことだよねぇ……」
というものでした。今思い返しても、非常に含蓄のある、至言だと思います。
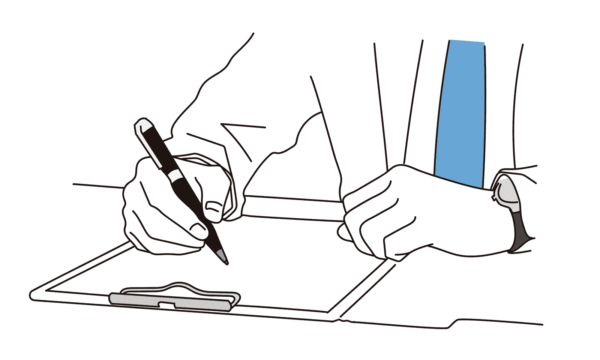
3.裁判は、「判決:勝ち負け」ではなく「和解」で終わることがほとんど
⑴ ほとんどの紛争は「100対0」ではない
実は、民事の裁判の場合、判決まで行くことは多くありません。
ほとんどの事件は、ある程度の主張・反論を双方にさせた後、裁判官が和解を勧奨し、当事者が裁判所を介して和解することで紛争が終了します。
例を挙げましょう。
XさんがYさんに対し、100万円の支払いを求めて裁判を起こしたとします。
Xさんの代理人弁護士、Yさんの代理人弁護士は、それぞれの依頼者から話を聴いて、主張をまとめた書面や主張を裏付ける証拠を裁判所に提出し、自分の言い分を認めてもらおうと頑張ります。
もっとも、裁判になるほどこじれた紛争では、どちらかが全面的に悪いということは多くありません(どちらかが100%悪いという事件の場合、悪い方の当事者には攻め手がありませんので、そもそも戦いになりません)。
裁判所に持ち込まれる事件の多くは、(程度の差こそあれ)双方に落ち度があります。
このため、ほとんどのケースでは、判決になったとしても、「100対0」ではなく、双方の落ち度に応じた判断が出るように思います。

⑵ 裁判所が和解を勧める“現実的”な理由
裁判所は、双方の落ち度や紛争の全体像が見えてきた段階で、「判決を書くとしたら、これくらいだと思う」という相場観(例えば、100万円全額ではなく、YさんからXさんに対して30万円を支払わせる)で、和解案を提示し、和解を勧奨します。
裁判官から和解案が出された場合、Xの代理人、Yの代理人は共に、和解案が妥当なものなのかを検証し、妥当な場合には、XとYそれぞれに、和解を勧めます。
裁判官は、判決になった場合の相場観をベースにして和解を勧めるので、和解を蹴ったところで、ほぼ同じ内容の判決が出される可能性が高いです。
(3) 和解の「分割払い」──支払いを受ける側にも意外なメリット
判決の場合、認容額の一括払いを命じられるのに対し、和解であれば、そのときの資力に応じた分割払いを和解条項に盛り込むことができます。
「自分が支払いを受ける側」の場合には、一括払いの判決を出してもらった方が良いように思いますが、支払いを命じる判決をもらっても、先方の資産を把握していなければ強制執行はかけられません。
先方の資産がわからなかったり、先方にまとまった資産がなかったりする場合には、和解で分割払いを定めた方が、時間はかかるものの任意に支払いを受けられることが多く、トータルの回収額で見れば、支払いを受ける側にもメリットがあるようです。
また何よりも、和解で事件が終結すれば、判決が出たり、判決に不満のある当事者が控訴したり、ということはありませんので、紛争が格段に速く解決し、経営者様が本業に100%注力できる環境を、早期に取り戻すことができます。

4.弁護士が和解を勧める「依頼者本位」の理由とは?
この記事をお読みの方の中には、裁判で、弁護士から和解を強く勧められた、という経営者もいらっしゃるかもしれません。
お気持ちとしては、「なぜ自社側の弁護士が、自社の言い分に寄り添ってくれないのか?」と思われるかもしれません。
しかし、弁護士が自分の依頼者に対して和解を強く勧める一番の理由は、お客様のためのリスクヘッジだということを、頭の片隅にでも置いておいて頂けますと幸いです。
5.“和解=妥協”ではない? 経営者にとっての戦略的メリット
ここまでお読みいただいた皆様はすでに理解されていると思いますが、裁判所からの和解提案であれば、提案を蹴ったとしても、それ以上に良い判決が得られる可能性は低いです。
裁判所は基本的に、判決での認容額をベースに和解提案をするからです。
そればかりか、和解提案を蹴ることにより、裁判の長期化とそれに伴う経営者様のストレスの継続や、一括払いのリスク、回収総額が下がるリスクなど、様々なデメリットがあります。
ですから、弁護士を通じて提案された裁判所の和解案を呑んで、早期に紛争を解決するというのは、経営者様にとって、合理的・戦略的な選択だと考えます。
\『和解の妥当性』を相談できるような顧問弁護士を持ちませんか?月額1万円で契約可能。ご紹介は無料!/
6.余談:和解成立が多い時期がある!?
ちなみに、和解が成立することが多い時期は、「年末」と「年度末」です。
昨年末にも、立て続けに和解がまとまりました。
経営者にとって、裁判というものは、たとえ相手に落ち度があったとしても、かなりのストレスになるようです。
やっかいな揉め事をひとつ終わらせて、新たな年や新たな年度を迎えたい、というお気持ちを皆様お持ちなのだと思います。
7.まとめ:和解は、未来志向の現実的な落としどころ
裁判における「和解」は、決して敗北でも妥協でもありません。
むしろ、当事者双方がこれ以上疲弊せず、現実的な落としどころを見つけて次に進むための“戦略的な選択肢”です。
弁護士が和解を勧めるのは、依頼者にとっての最善を見据えての提案であり、「目先の勝ち負け」にとらわれない広い視野に立った判断です。
経営者として次の一手を見出すためにも、「どう終わらせるか」を冷静に考える視点を持っていただければと思います。
(了)
\和解すべきか迷ったら、企業法務に強い顧問弁護士と一緒に考えませんか?月額1万円で契約できる弁護士を無料紹介/
記事を執筆したE弁護士と当会のご案内
\ 落ち着きと安心感、頼もしい! /
新宿区(新宿御苑駅近く)にて開業中の40代男性・E弁護士。上智大学卒。
弁護士より:『些細と思うことでもお一人で抱え込まず、御社の”かかりつけ弁護士”としてお気軽にご相談ください』

E弁護士プロフィールE弁護士ブログ記事
●ご指名の上、紹介申込みできます!
webフォームでの顧問弁護士無料紹介申込み
\弁護士全員が顧問料1万円/