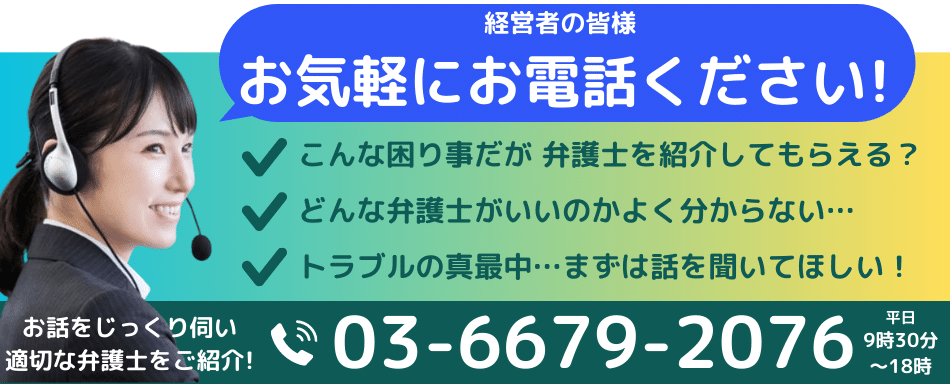はじめに:社内不正と司法取引の関係
L.A.P.中小企業顧問弁護士の会の弁護士のGです。
皆様は「司法取引」という制度をご存知でしょうか。
司法取引という言葉は、海外映画やドラマのイメージが先行しがちですが、実は2018年から日本でも制度として運用されています。
犯罪者のための制度のように思われるかもしれませんが、実は、これまで司法取引が用いられたケースは、企業に関係する重大な不正に関するものなのです。
本記事では、
✅ 日本の司法取引制度の基本的な仕組み
✅ 企業がどう関係するのか
✅ 実際にどんなときに検討すべきか
について、中小企業の経営者向けに 弁護士がわかりやすく解説していきます。
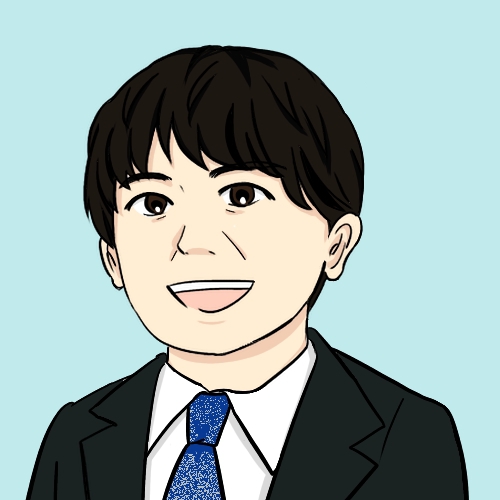
1.司法取引とは?意外と知られていない企業との関係
1-1. 日本でも司法取引の制度はあるのか?
司法取引は、正式には「協議・合意制度」と呼ばれ、刑事訴訟法第350条の2以降に規定されています。
特定の犯罪に関し、他人の犯罪の捜査や公判に協力することで、自分または自社の処分を軽減してもらう制度です。
日本で導入されたのは2018年と比較的新しく、適用件数も少ないため、あまり広く知られていないのが実情です。
1-2. 企業と司法取引がどう関係するのか?
実際に司法取引が適用された事件はすべて、企業が関与する経済犯罪や組織犯罪でした。
司法取引というと、従業員が会社を内部告発して「自分の刑を軽くしてもらう」といったイメージがあるかもしれません。
しかし、日本における適用例の多くは、会社 が“主体となって”捜査に協力し、企業自体への刑事処分を回避するという形です。
つまり、司法取引を結ぶ主体が「会社(法人)」であるケースが多いというのが、現時点での日本版司法取引の運用となっています 。

2.企業が司法取引を検討するタイミングとは?
2-1. 社内での不正発覚が「捜査前」であることがカギ
企業が司法取引を現実的な選択肢として検討できるのは、捜査機関が正式に動き出す前に社内で不正が発覚した場合です。
たとえば、内部通報や社内監査で役員や従業員の法令違反が明らかになったとき、企業側がいち早く情報を整理し、捜査機関に協力を申し出ることで、企業への責任追及を免れる可能性があります。
2-2. すぐに通報すべきか?他の選択肢との比較
ただし、司法取引を行うには、当然ながら不正に関する情報を捜査機関に提供する必要があります。
それにより、事態が大きく公になるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
たとえば、
- 被害者(取引先や顧客など)との示談によって解決できる場合
- 行政指導により業務改善で済む可能性がある場合
- 社内処分と再発防止策の徹底によってリスク評価を下げられる場合
などは、司法取引以外の選択肢で収束を図れるケースもあります。
いずれにせよ、専門家による見立てと戦略的判断が不可欠です。
2-3. 実際に使われた司法取引の事例とは?
日本で初めて司法取引が適用されたのは、海外の公務員への贈賄事件でした。
2件目は、有価証券報告書の虚偽記載事件。
どちらも企業が関与する重大な経済犯罪でした。
1件目では、企業が積極的に捜査協力を行った結果、起訴を免れることができました。
このように、司法取引は「会社に刑罰が課されるという、最悪の事態を回避する交渉材料」として活用されることがあります。

3.顧問弁護士がいれば、リスク発覚後の初動も安心
3-1. 経営判断が問われる“初期対応”こそ冷静に
社内で重大な不正が明らかになったとき、経営者が単独で判断を下すことは非常に危険です。
- 捜査機関に報告すべきか?
- 内部で処理できる可能性はあるか?
- 企業の社会的信用を守るにはどうすべきか?
こうした判断には、刑事・行政・企業リスクに通じた顧問弁護士などの専門家の知見が欠かせません。
3-2.不正を防ぐために、日頃から整えておくべきこと
そもそも、こうした重大事案を未然に防ぐためには、
- 社内規程の整備
- 職務権限の明確化
- 内部通報制度の導入
- 定期的な研修や倫理教育
といった、日頃の就業環境の整備やコンプライアンス体制の構築が極めて重要です。
こうした整備を後回しにしていると、不正が起きた際に「企業の管理責任」が問われ、より大きなダメージを被ることになります。

まとめ:司法取引を“知っておくこと”が会社を守る
司法取引は、特殊な制度でありながら、企業にとっては刑事責任を回避できる最後のカードになり得ることもあります。
「そんな制度があったのか」と後から知るのではなく、
いざというときに備えて、経営者として制度の存在を知っておくこと自体がリスクマネジメントです。
そして、刑事事件にも対応している顧問弁護士がいれば、
- 重大事案が発覚した際の初期対応
- 公にすべきか、社内で収めるべきかの判断
- 捜査機関とのやり取りを含めた戦略的対応
まで、落ち着いて対処できるようになります。
「こんな話、うちには関係ない」と思っている間に、突然の不正が発覚する。
そうした事態にならないように、万が一に備える意味でも、日頃から相談できる体制を整えておくことをおすすめします。
(了)
記事を執筆したG弁護士プロフィールと当会のご案内
\ 気さくで朗らか、説明が分かりやすい /
新宿区内の法律事務所の共同代表0代男性・G弁護士。とても話しやすく説明がわかりやすい弁護士です。
弁護士より『「お客様と二人三脚」がモットーです。法的問題に限らず「取引先や従業員との付き合い方」のようなさまざまなご相談に対応します。ご相談は平日夜9時まで承りますので遅い時間でもお気軽にご相談ください』
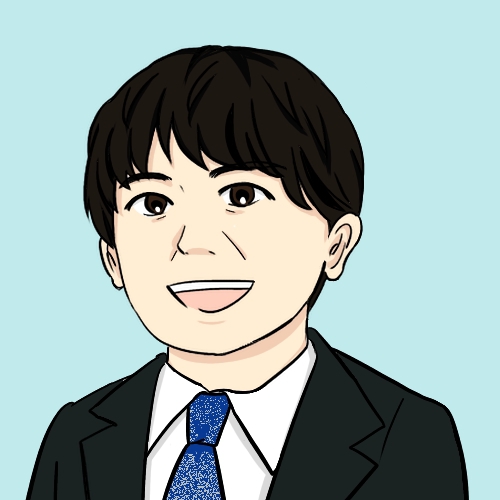
G弁護士プロフィールG弁護士ブログ記事
●ご指名の上、紹介申込みできます!
webフォームでの顧問弁護士無料紹介申込み
\弁護士全員が顧問料1万円/