「顧問弁護士を変えたい。でも、何か問題になることはないか?」とお思いの経営者様は少なくないと思います。
顧問弁護士への不満――「メールの返信が遅い」「業界知識に乏しい」「話がかみ合わない」――が積み重なると、日々の経営判断に支障をきたすことが多々あります。
一方、顧問弁護士の変更にはデメリットもありそうで、ご不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、中小企業が顧問弁護士を変更すべきタイミングや判断基準、変更をスムーズに行うための手順を、弁護士の視点から整理してお伝えします。
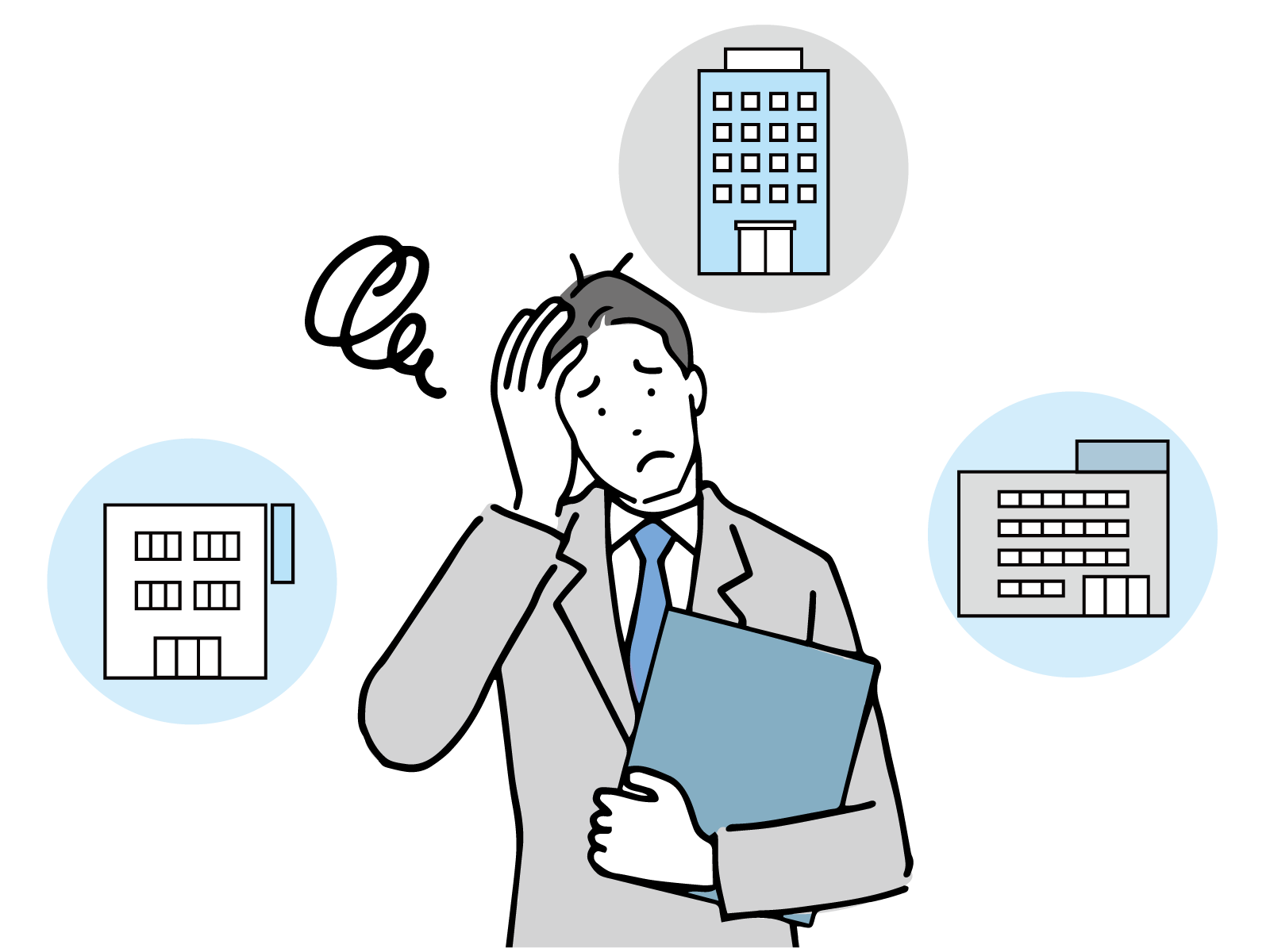
「顧問弁護士を変更したい」経営者からの相談は少なくない
中小企業のお客様とお仕事をさせて頂くようになって十数年経つのですが、十数年もやっていますと、ちらほらと「現在の顧問弁護士を変更したい」というご相談をいただくことがございます。
そこで今回は、
・経営者が顧問弁護士を変更したいと思う【理由】
・顧問弁護士を変更する際に注意すべき【ポイント】
・顧問弁護士を変更するのに適した【タイミング】
・顧問弁護士を変更する場合の【具体的手順】
について解説いたします。
顧問弁護士の変更をお考えの経営者様にはぜひお読みいただき、より合う弁護士選びや後悔のない弁護士変更のお役に立てれば幸いです。
そもそも顧問弁護士の変更はできるのか?
そもそも、「今の弁護士との顧問契約をやめることなんてできるのか?」という疑問をお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんが、顧問契約書に書かれたルールに則っていれば、法的には何ら問題ありません。
弁護士と顧問契約を結ばれた際には、必ず、顧問契約書を締結していると思いますが、一般的な顧問契約書には必ず、有効期限や、「顧問契約を更新しない場合には満期の○ヶ月前までに告知すること」、といった条文が入っているはずです。
このルールにのっとって解約のお手紙やメールを送れば、現在の顧問弁護士との契約は解約することができます。
解約の理由を聞かれたら、どう答えるべきか?
解約を伝えた際に、弁護士から解約の理由を聞かれるかもしれませんが、その場合、特に答える必要はありません。
顧問契約書において、解約の理由を説明せよ、などという条文は入っていないはずですし、法律上、そのようなケースでの理由の説明義務を定めた条文は、私の知る限り存在しません。
それまで契約をしていた弁護士としても、「顧問契約をやめたい」という方に、執拗に理由の説明を求めるというのは、考えにくいところです。
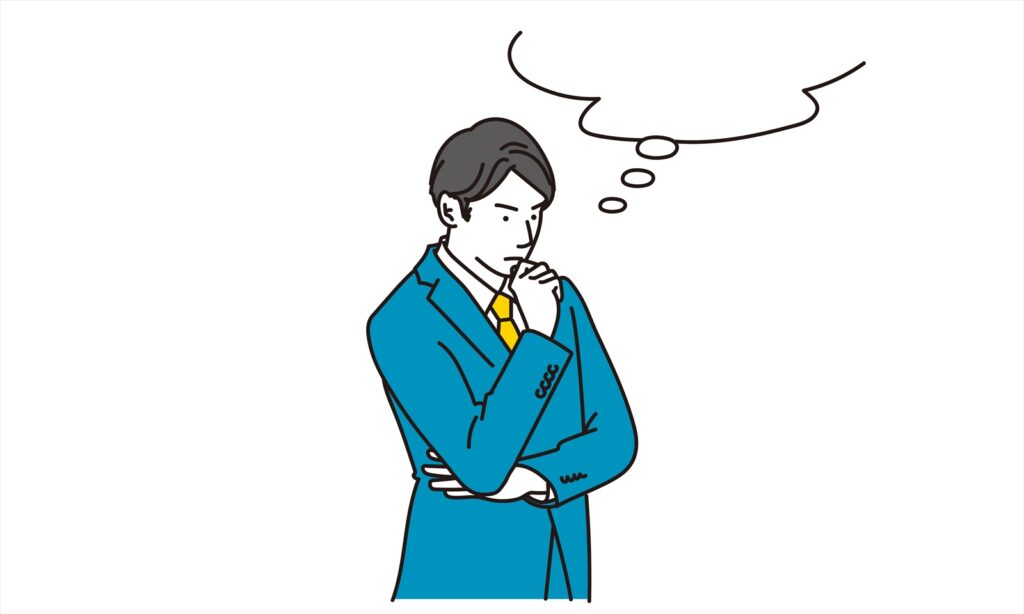
今の顧問弁護士への不満・変更したい理由を分類すると
ではここからは、「経営者様が顧問弁護士を変えたいとお考えになる本当の理由は何なのか」を考えてみたいと思います。
「現在の顧問弁護士を変えたい」というご相談を頂いた際、「ぜひとも弊所にご依頼ください!」と飛びついてもいいのですが、それも何だか品のない話ですので、まずは「なぜ顧問弁護士を変えたいと思われたのですか?」という質問をさせていただいております。
その際にお聴きする個別のご事情はいろいろあるのですが、多くは、今の顧問弁護士について
①「相談しにくいと感じる」
(1)性格・相性のミスマッチ
(2)連絡(相談)手段のミスマッチ
②「コスト(顧問料)が高いと感じる」
に分類できるように思います。
変更したい理由①:「顧問弁護士に相談しにくい」
1つ目の「相談しにくい」をもう少し掘り下げますと、その中には、【性格・相性のミスマッチ】と、【連絡(相談)手段のミスマッチ】があるようです。
それぞれご説明いたします。
<相談しにくい>具体例(1) 性格・相性のミスマッチ
「顧問弁護士との相性が合わない」ケースです。
この【性格・相性のミスマッチ】には、
「話しにくい」
「当社の不祥事を話すと怒られそうで相談しにくい」
「法律はこうなっている、という説明ばかりで、結局当社がどうすればいいのかを教えてくれない」
などがあるようです(私も気を付けます)。
ここで、弊所に「顧問弁護士を変えたい」と言ってこられた方の例をご紹介しましょう。
<顧問弁護士変更の実例> ある飲食店経営者の例
ある飲食業の経営者が弊所にいらして、このようなお話をされました。
「ある組織で知り合った、自分と同い年の弁護士と顧問契約していたが、当社の担当者が顧問弁護士に相談しづらくなってしまい、社として顧問弁護士を変えることにした」
そこで、後日その会社の担当者様とお会いしたところ、とても素晴らしい方でした。
また(私の思い込みでなければ、ですが)その担当者様からはその後、日々の相談もお気軽にしていただいており、その会社様とも現在に至るまで平穏に顧問契約を結んで頂いております。
つまり、相談しづらい=担当者様と前の弁護士との相性の問題だったのです。
このような例もありますので、「本当に相性というのは大切だ」と思う次第です。
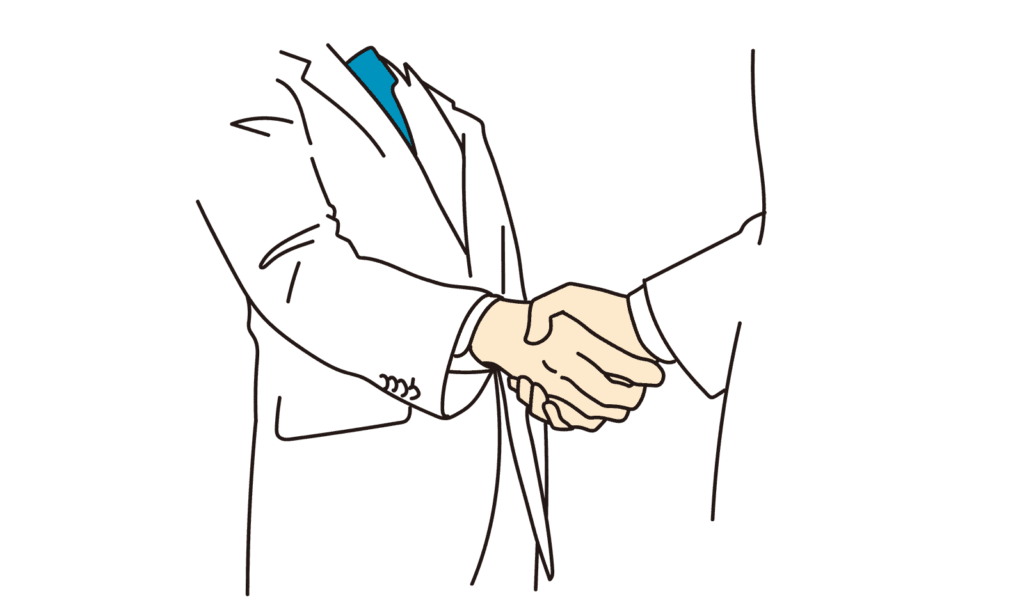
\相性の合う弁護士と契約したいなら・最低2人と面談を・こんなベテランも!? 無料紹介はこちら/
<顧問弁護士に相談しにくい> 具体例(2) 連絡(相談)手段のミスマッチ
【連絡(相談)手段のミスマッチ】というのは、弁護士と連絡のつく手段や弁護士からの回答方法のミスマッチを指します。
弁護士と電話がつながりやすいか・オンラインや対面が得意か
例えば、
・口頭のやり取りで相談したい
・出来るだけ会って話したい
という経営者の場合、
・電話がつながりやすい弁護士
・オンライン相談に対応している弁護士
・対面での説明が得意な弁護士
が良いでしょう。
弁護士がメールが得意か、チャットアプリに対応しているか
一方、
・弁護士の見解を社内の別部署や取引相手と共有したい
という場合には、
・メールや文書での回答が得意な弁護士
が良いでしょう。
また昨今では、
・通信ツールとして「LINEやSlack等のチャットアプリしか使わない」という経営者様
もかなり増えています。
そういった方の場合には、
・チャットアプリを導入している弁護士でないと話にならない
ということになるでしょう。
連絡(相談)手段が合うかどうかは、重要なファクター
つまり、経営者に合った手段に弁護士が対応していることが大事なのです。
経営者にとって、顧問弁護士は日々の業務のパートナーにあたるため、こういった【連絡(相談)手段のミスマッチ】は私が思う以上に、経営者の経営判断に影響しているようです。

変更したい理由②:「顧問弁護士のコストが高いと感じる」
顧問弁護士を変更したい理由の2つ目「コスト(顧問料)が高いと感じる」というのは、実は1つめの「相談しにくい」と関係する部分があります。
「相談しにくい」場合、「その割にこのコストは高い」と感じやすいからです。
先に挙げた、飲食業の経営者様の例でも(同社の担当者が顧問弁護士に「相談しづらかった」例)、顧問料は一般的な顧問弁護士の相場だったようです(つまり月額5万円程度)。
経営者様は「月に何万円も顧問料を払っているのに、相談しづらいのでは意味がない」と思われたからこそ、「顧問弁護士を変更しよう」という行動に出られたのでしょう。
顧問料に何が含まれているかの事前確認を
もっとも、「コストが高いと感じる」理由にはもう1つあるように思います。
顧問料に何が含まれるのかについて
契約前のすり合わせが不足していた
ということです。
この点について経営者様と弁護士の間に意識のズレがあると、経営者様は「コストが高い」という意識を持たれるようです。
ですので、顧問弁護士を既に導入されている経営者様におかれましては御社の顧問弁護士が、①「相談しにくい」②「コストが高いと感じる」という状態になっていないか、今一度ご確認ください。
もしどちらか1つでも当てはまる場合には、顧問弁護士変更を検討されても良いかもしれません。
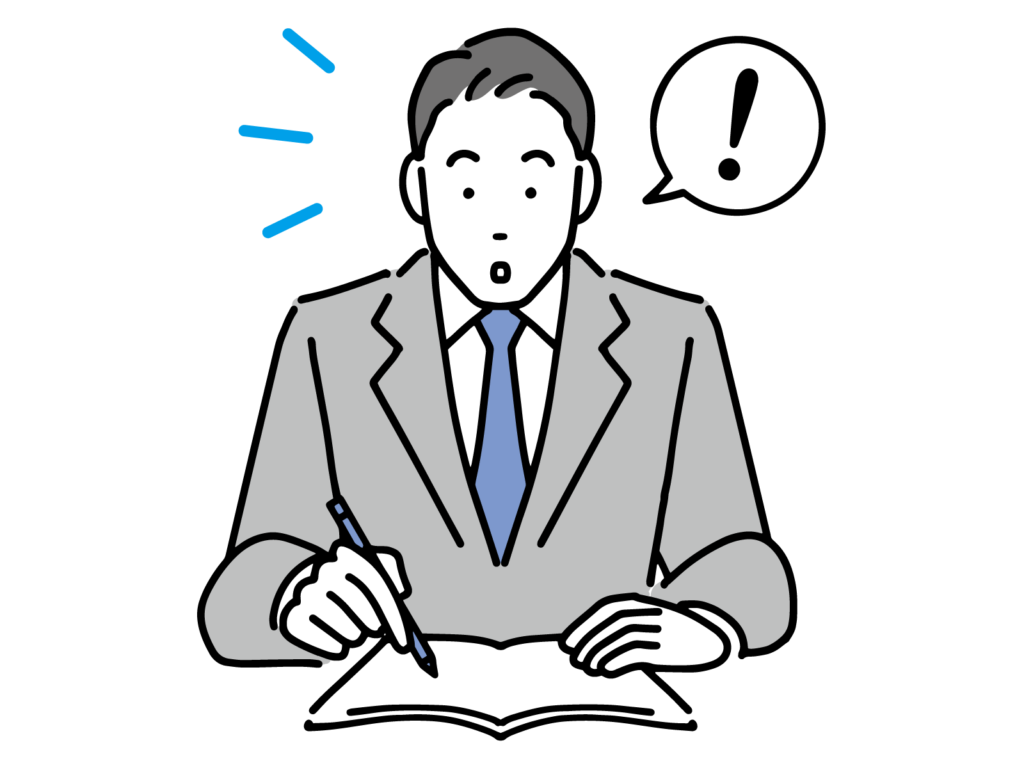
\顧問弁護士は月額1万円で雇える時代!無料紹介はこちら/
顧問弁護士の安易な変更にはデメリットも
もっとも、顧問弁護士の安易な乗り換えにはデメリットもあります。
2つのデメリットをご紹介します。
デメリット① 御社の社風等を理解している弁護士を切ることになる
もし現在の顧問弁護士が「相談しにくい」人物だったとしても、顧問弁護士を一定期間務めていた以上は、御社の社風や特殊事情、御社が所属している業界の事情などについて、ある程度熟知しているのではないでしょうか。
が、その業界の事情に詳しくない顧問弁護士に変えた場合には、これらすべての点について、また一から理解してもらわないと話が進まないことになります。
特に、御社が特殊な業界に属されている場合には、新しい弁護士が業界の事情に精通するまで、かなりの期間を要することもあります。
一方、現在の顧問弁護士との関係性が希薄であり「当社のそういう深いところまで理解していない」ような弁護士でしたら、顧問弁護士変更になんら問題は生じないでしょう。

デメリット② 安い顧問料の弁護士に切り替えた結果、却ってコスト高になることも
また「コストが高いと感じる」からといって、安易に顧問弁護士を変えると、却ってコスト高になることもあり得ます。
昨今は、見た目の顧問料の安さ(月額5千円未満とか月額1万円未満など)を打ち出す弁護士も増えてきました。
が、「その安い顧問料でどれだけのことをしてもらえるのか?」という視点を持っていただきたいのです。
安い顧問料に、何が含まれているかの事前確認を
馬鹿正直にいいますと、L.A.P.中小企業顧問弁護士の会でも、顧問料1万円(税別)プランの場合には、対応可能な業務時間を「月に2時間まで」と設定させていただいておりますので、あらゆる会社様において御社の抱えるすべての法的問題が顧問料1万円で解決できる、というわけではありません。
つまり御社のご事情(依頼したい内容や業務量)によっては、安い顧問料を掲げる弁護士に切り替えた結果、却ってコスト高になることもあるのです。
(その代わりといってはなんですが、私は、経営者様が月額1万円での顧問契約を希望される場合、ご契約前の面談時にて「2時間でどれだけの作業ができるのか」「納期はどのくらい見てもらえばいいか」を、可能な限り詳細にお話させていただくようにしています)

顧問弁護士切り替えの「タイミング」や「具体的手順」
ここまで長文をお読みいただきありがとうございます。
ここからは、顧問弁護士を切り替える「タイミング」や「具体的手順」をご説明いたします。
顧問弁護士を切り替える「タイミング」はいつがいいのか?
まず、「タイミング」ですが、この文章の冒頭でもご説明したとおり、これまでの顧問弁護士との契約期間の問題があると思いますので、その弁護士との契約満期に合わせる、というのが一つの好機になります。
まずは、今ご契約されている弁護士との顧問契約の内容をご確認ください。
切り替えにふさわしくない「タイミング」もある
また、「このタイミングでの切り替えは止めた方がいい」というポイントとして、動いている事件があるときはやめた方がいい、ということが言えると思います。
ある相手と訴訟や交渉案件が続いているときに、弁護士の対応が不満で顧問弁護士の切り替えを検討されることもあるかもしれません。
しかし、訴訟や交渉の途中で弁護士を変えるというのは、開腹手術の最中に主治医や執刀医をいきなり変えるようなものです。
係争が起きている最中の顧問弁護士変更は、より悪い方に転ぶ可能性が高いと思います。
顧問弁護士変更のタイミングと手順
顧問弁護士を変えるタイミングや手順について、ざっくりまとめますと、
step
1現在の顧問弁護士との契約が満期に近づいている
step
2いろいろ細かい不満があるが、大きなトラブルがないタイミング
step
3次の顧問弁護士候補を探し始める
step
4良い弁護士が見つかったら、現在の顧問弁護士との契約満期に、新しい顧問弁護士に切り替える
というのが良いと思います。
顧問弁護士変更の実務的な手順は?
「顧問弁護士の変更を考えているが、どのような手順で進めたら良いのかわからない」という方もいらっしゃると思います。以下では、手順の一例をお示しいたします。
新しい顧問弁護士を探すに当たって
新しい顧問弁護士を探すに当たってやるべきことのリストを作成いたしました。
各会社様ごと、ご事情が異なりますので、「あくまで一例」とご理解下さい。
step
1新顧問弁護士用、困りごとのメモを作る(どんな相談事が多いか、現在喫緊の課題は何かを箇条書き)
step
2顧問候補と比較面談(2名程度/面談は30~45分が目安)
step
3社内判断(代表・役員レベルで決める)
新しい顧問弁護士を検討する際は、必ず面談を!
新しい顧問弁護士をお探しいただく際には、必ず弁護士と一定の時間、面談をして話していただくことをお勧めいたします(新しい顧問弁護士候補がWEB会議に対応しているようであれば、WEBでも良いと思います)。
顧問弁護士を決めるというのは、億劫な作業でもあると思いますし、特に、経営者様自らがこの作業を担当される場合には、お忙しい業務の合間を縫っての作業になると思います。
ですが、安易な乗り換えで相性の合わない弁護士に当たってしまったら、それまでの顧問弁護士と同じように、細かい不満を抱えながら、毎月の顧問料という固定費を払い続けることになります。
面談で話す中には、メールやLINEではわからない、その人その人の「人となり」があらわれます。
(このあたりの話については、以前別記事でもコメントさせていただきました。お時間がございましたら、下記の記事もご高覧下さい)
\【関連記事】/
この時代にあってなお、弁護士の私が初回面談を”対面”にこだわる理由
ぜひ、弁護士の「人となり」を見極めた上で、顧問契約の乗り換えをご検討下さい。
\弁護士2名を無料ご紹介・相性確認面談だけでもOK/
新しい顧問弁護士が見つかったら
新しい顧問弁護士が見つかった場合に行うべきことについても、リスト化いたしました。
このあたりは事前に厳密に考えておかなくても、「この人に新しい顧問になってほしい」という弁護士が見つかった段階で、その弁護士にご相談いただいても良いように思いますが、参考までに記します。
step
1開始時期の合意
→ この記事の上の方でも申し上げましたが、今の顧問弁護士との契約が終わるタイミングでの切り替えをお勧めいたします。
step
2現顧問へ終了の連絡
→ 新しい顧問弁護士(の候補者)から、顧問弁護士就任の内諾が取れたら、今の顧問弁護士に解約を申し入れましょう。
「解約申し入れは〇カ月前までに」という契約になっていることもありますので、その期限を過ぎないようご注意ください。 特に理由の説明はいりません。契約の終了時期と、これまでの謝意を簡単に述べる程度で良いと思います。
step
3新しい顧問弁護士の周知(社内の窓口と連絡方法を決める)
→ 弁護士マターに対応するスタッフが社内にいる、という場合には、そのスタッフの方に新しい顧問弁護士の存在と、切り替わりの時期をきちんと伝えて下さい。 WEB会議でも良いので、社内スタッフと新しい顧問弁護士との顔合わせをしておくと、以後のご相談がスムーズに進むと思います。
顧問弁護士を変更する場合のポイントまとめ
顧問弁護士の変更を検討される際には、新しい弁護士が、
・相性は合うか
・連絡(相談)手段は何に対応しているのか
・この顧問料で、どこまでの業務を、どのくらいのスピード感でやってもらえるのか
等について、契約前にきちんとご確認いただくことをお勧めします。
(手前味噌になりますが、契約前の弁護士との面談のチェックポイントについては、L.A.P.中小企業顧問弁護士の会の事務局が、【弁護士の面談チェックリスト】を作成しております。こちらもよろしければご活用ください)
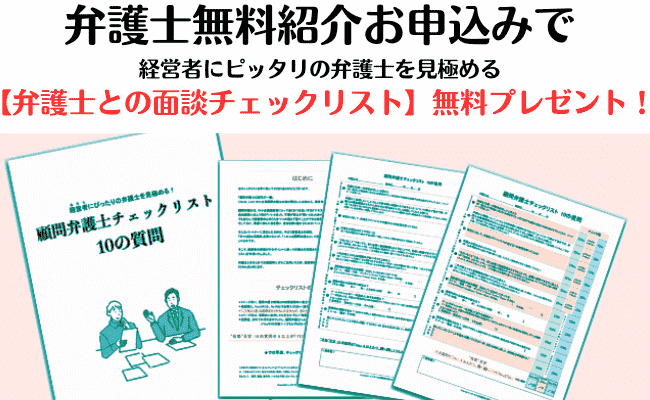
顧問弁護士として自社にふさわしいかを面談時に見極めるための「顧問弁護士チェックリスト」です。弁護士無料紹介お申し込みをいただいた方全員に無料プレゼント
また、切り替えに当たっては、これまでの顧問弁護士との契約が切れるタイミングでぴったり切り替えると、角が立たず、かつ、シームレスな顧問弁護士業務を受けられやすくなると考えます。
1社でも多くの中小企業様が、御社にフィットする顧問弁護士と出会われることを願ってやみません。
(了)



