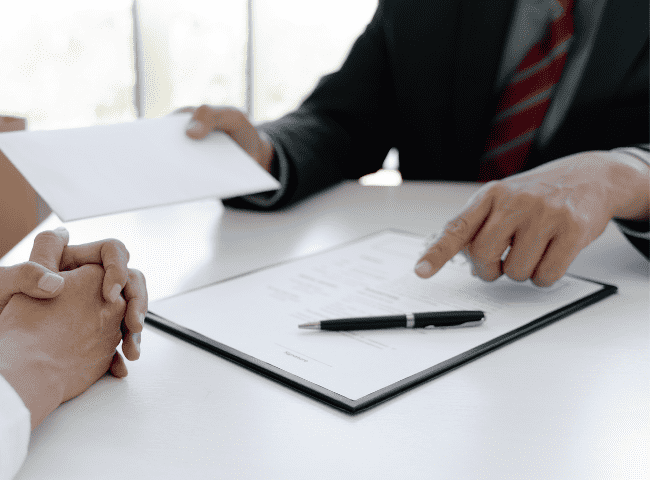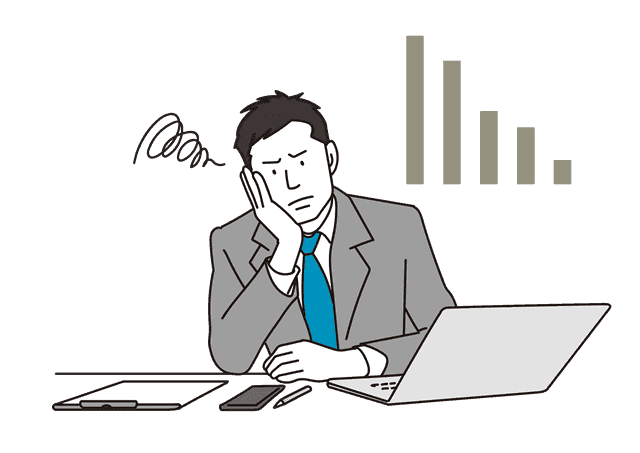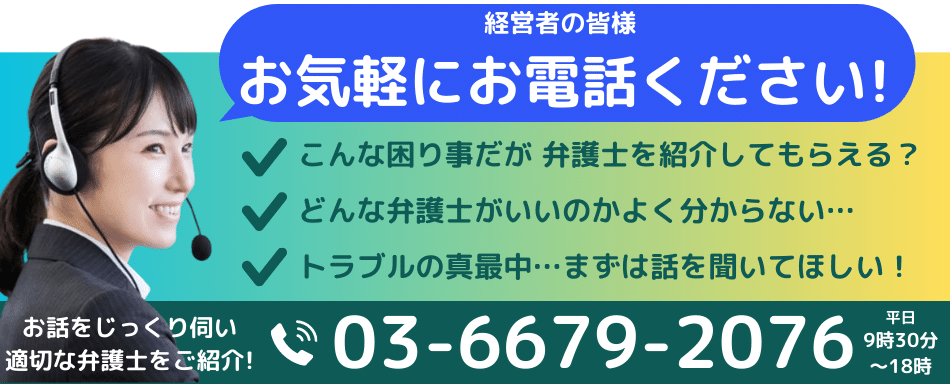L.A.P.中小企業顧問弁護士の会 コーディネーター・中川のブログです。
中小企業経営者の皆様、会社経営において様々な手続きが必要になったり困りごとが起きたりした時、どの専門家(士業者)に相談しますか?
税理士、社労士、司法書士、弁護士など、さまざまな専門家が会社経営をサポートしていますが、
・それぞれの士業の役割の違い
・こんなときに活用できるという業務や領域
があります。
そこで今回は、それらについて専門用語をなるべく使わずに、分かりやすく解説いたします。

1.税理士:税金に関する手続きや相談
税理士の役割
ほとんどの中小企業経営者は、税理士とはおつきあいがありますよね。
税理士は、その名の通り「税」に関すること全般の専門家。
税理士に任せることの多い月々の記帳代行も、記帳データが、毎年の決算(税務申告)の大もとになるからこそ税理士に依頼するのです。
また、税理士は、会社の月々のお金の流れを見ることのできる立場にいるため、そこから派生して「お金がらみ」のさまざまな分野のアドバイスをすることができます。
具体的には下記のように多岐に渡ります。
税理士を活用できる業務や領域
・月次の記帳(ほかに記帳代行専門業者もいます)
・決算・確定申告業務の代行(税務申告、納税者本人か税理士しかできない)
・税務調査対策
・節税の相談
・経営相談(財務状況を鑑みてのアドバイス、経営コンサルタントの領域と重なる)
・融資を受ける際のアドバイス
・各種補助金や助成金の手続き代行(社労士でも行う方が多い) など
ただ実際問題としては、貴社の税理士が行う業務の範囲は、税理士のスタンス(その会社にどこまで・どうかかわるか)によって、大きく異なってきます。
また、会社の成長に応じて経営者が税理士に求めるものも変化します。
たとえば、起業した当初は、「税理士は記帳代行と税務申告だけやってもらえれば十分」と経営者が思っていても、会社が成長するにつれ「節税のアドバイスが欲しい」「当社に合った補助金を提案してほしい」といった要望も湧いてきます。
経営者にとっては一番身近な専門家(士業者)ですから、税やお金に関わる疑問や要望を気軽に相談できる人がいいと思います。
また記帳や決算以外のサービスも提供できる税理士とおつきあいができるといいですね。

2.社会保険労務士(社労士):人に関する手続き
社労士の役割
社員数が10数名以上の会社では、社労士を活用されている経営者の皆様は多いのではないでしょうか。
社労士は、人(労働者)に関する手続き全般の専門家です。
主な役割としては、労働者の入退社の手続(社会保険等)や、労働者の給与の掲載、労働者がらみのトラブル対応、就業規則など労働者の関わる規程の整備、などです。
労働者に関わることはたいていが守備範囲です。
実は、「社労士がいないと社会保険の手続きや給与計算ができない」ということはありません。
しかし、会社がそれなりの規模になってくると手続きの件数やデータが多くなってきますので、
手続きや給与計算に漏れや間違いがないように社労士に依頼しよう
という考え方が出てきます。
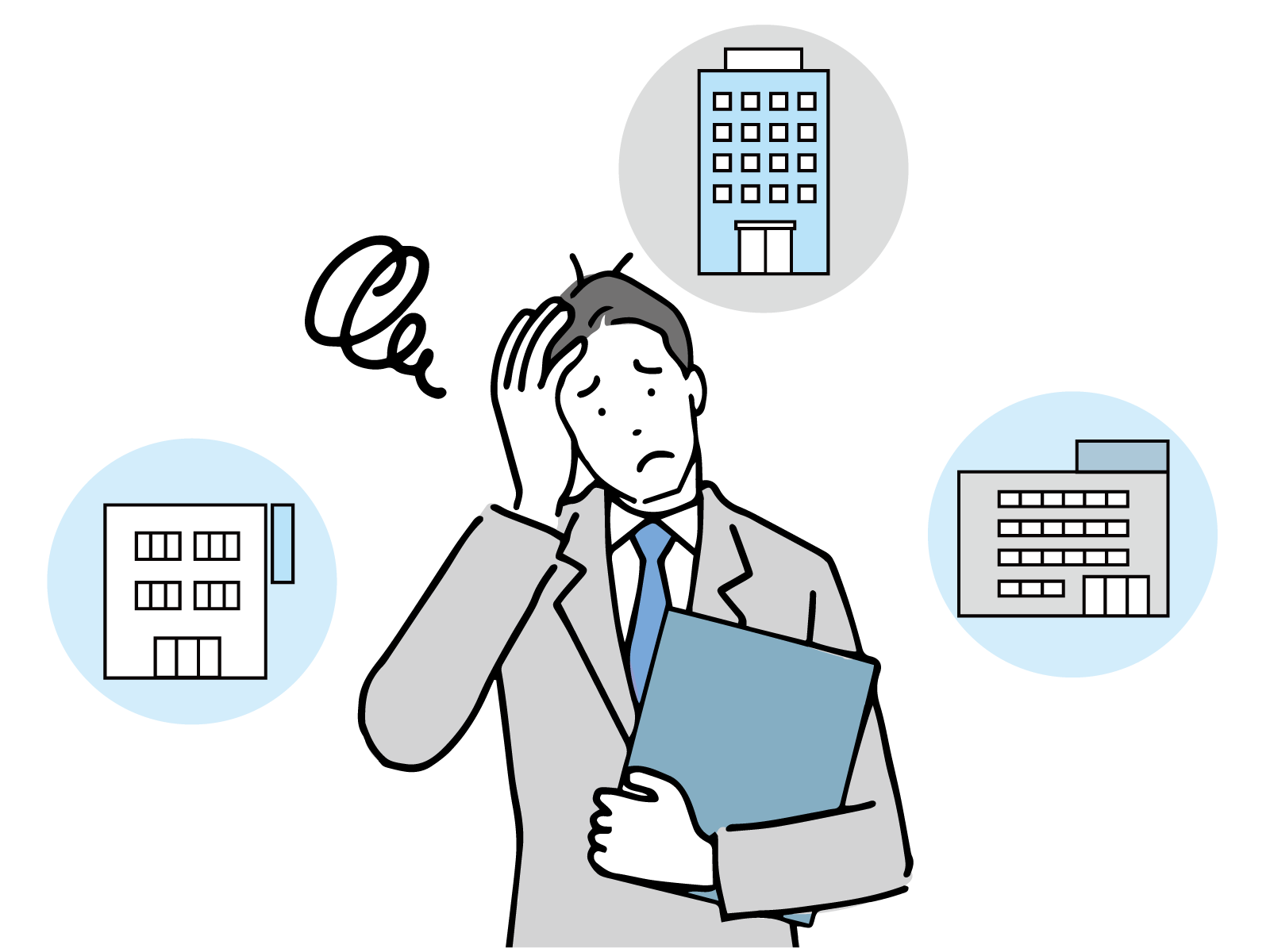
社労士を活用できる業務や領域
社労士を活用できる分野は、具体的には下記のように多岐に渡ります。
・労働者の入社退社や異動に伴う各種手続きの代行
(平たく言うと、労働者の社会保険などの各種手続き代行。書類を作成したり必要機関に提出したりします。雇用主もしくは社労士しかできない)
・勤怠管理や給与計算代行
・人事労務に関する相談、労働問題に関する相談(ここは弁護士も対応可能領域)・・・(*)
・就業規則など人が関わる規定の整備(ここも弁護士が対応可能な領域)
・その他の規程規程の整備(ここも弁護士が対応可能な領域)
・各種補助金、助成金申請手続き(ここは税理士も対応可能領域) など
最後に挙げた「補助金や助成金の申請代行」ですが、最近これに力を入れている社労士が増えていると聞きます。
その理由は、労働者の採用や能力開発等に関わる補助金や助成金がたくさんあるためだと思われます。
また、社労士は職務柄、「人事担当者や、給与計算担当者としか面識がない」という会社も多いかもしれませんが、上述のように補助金・助成金や労働問題も守備範囲とする社労士もいますので、経営者様も年に一度くらいは社労士とお話をされると必要な情報やアドバイスが得られるかもしれません。
(*)特定社会保険労務士(特定社労士)について
特定社労士試験に合格し「特定社労士」として登録すると、労働紛争の裁判外での解決手続き(あっせん調停等)も行うことができます。
(この分野は弁護士の対応可能領域でもあります)。

3.司法書士:各種登記の手続き
司法書士の役割
登記には、大きく2つの分野がありますが、
・商業登記(会社の設立、変更、解散等)
・不動産登記(売買、相続、抵当権設定等)
いずれの登記でも司法書士が事務手続きを担います。
登記も「司法書士がいないと手続きできない」というものではありません。
しかし、経営者にとっては手続きが煩雑なため、
手続きを確実に行いかつ経営者の時間と手間を軽減するために司法書士に依頼する
というケースが多いようです。
なお、登記の手続き(法務局への書類作成と提出)は、当事者が自身でできない場合は司法書士に依頼することがほとんどですが、弁護士も代理人として登記申請することができます。

司法書士を活用できる業務や領域
司法書士の具体的な業務や領域は下記の通りです。
・会社を新たに設立した際の登記手続き
・会社の役員が変更になった際の登記手続き
・会社の本店を移転した際の登記手続き
・会社の事業目的を変更した際の登記手続き
・会社の不動産を売却した際の登記手続き など
会社設立時の登記をしない経営者はいませんが、各種変更(「役員変更」や「本店移転」「事業目的の変更」など)の場合は、「うっかり」してしまうかもしれませんね。
しかし登記は「義務」であり、手続き期限が決まっていますので、確実に実行する必要があります。
ですので下記のことを押さえておきましょう。
・「会社の不動産に関すること」や「商業登記に記されていること」を変更する際は登記変更が必須
・登記の手続きには期限がある
・多くは司法書士に依頼する。あらかじめ司法書士に話をしておくと仕事を依頼しやすい
最近は、「会社設立の登記は費用の節約のため自分でやる」という経営者もいらっしゃるようです。
が、会社設立後に何らかの商業登記の変更をする場合は、経営者ご自身がすでにかなり忙しくなっている時期なはずです。
ですので「何が何でも自分でやる」のではなく、専門領域は専門家に依頼する方がベターだと思います。
よって、「必要な時がきたらお願いする司法書士さん」を決めておかれると良いと思います。
<備考>
特定の司法書士は、「簡裁訴訟代理等関係業務」の認定を受けると、簡易裁判所の民事事件で訴訟などの代理人になることができます(この分野は弁護士の対応可能領域と一部重なる)。
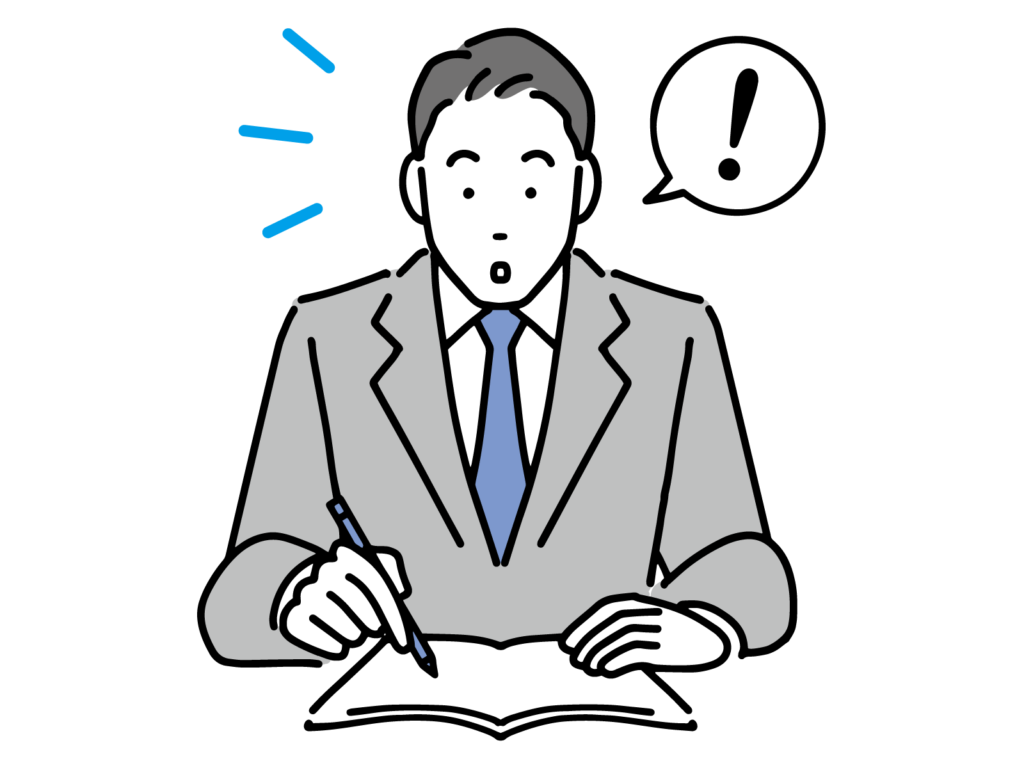
4.弁護士:法律が絡むことすべて
弁護士の役割
弁護士は、法律が絡むあらゆる問題を解決する専門家です。
具体的には、
・法的に困っている方の法律相談に乗ったり
・裁判の代理人となったりして依頼者を支援
します。
しかし、会社経営者にとって、弁護士は上述の士業ほどには「なじみがない」のではないでしょうか。
経営者は、目の前の問題に「法律が絡んでいること」自体に気づきづらい
なぜならば、ひと口に「法律が絡む問題」といっても大変範囲が広く、経営者自身がその渦中にいるのかすら判断がつかないケースが多いからです。
(弁護士がサポートする領域であることに気づきづらい)
例えば、下記のような状況なら「法律が絡む問題」との見当はつきやすいのですが、
・元従業員から不当解雇だと訴えられた
・会社の作った製品を購入し使用したお客様がケガをした など
仮に、下記のような状況となったとき、多くの経営者にとって「法律が絡む」と判断することは容易でありません。
①海外から食品を輸入して販売する
②美白化粧品の広告キャッチコピーを社員に作らせた
③同一人物によるネット上でのしつこい中傷に困っている
④売掛金を支払わない取引先がいて、
債権時効中断の手続きのために6ヶ月ごとに
請求書を送っているから問題はない など

日常業務に法律が絡んでいると気づかないとどうなるか?
ちなみに、これらには下記のような法律上の問題があります。
①のケース→
食品衛生法により
「検疫所への届け出が必要」なのですが、
何も知らなければスルーしてしまいそうです。
②のケース→
薬機法で様々な制限を受けます。
③のケース→
名誉棄損や営業妨害の問題です。
④のケース→
よく誤解なさっている方がいますが、
請求書を送り続けただけでは時効の中断はできません。
このように日常的に行っている業務に、実は法律がかかわっており、対応を謝ると大きなトラブルになったり金銭的なダメージを被ったりする可能性もあります。
とはいえ、そういった可能性に、経営者の皆様がなかなか気づかないのは無理もないことです。

日常の業務に法律上のリスクがあるかを教えてくれるのが弁護士
つまり、「それが弁護士に相談すべきこと否かを判断すること」自体、多くの経営者にとって判断が難しいのです。
であるならば、「業務上のリスクを下げて安心して会社経営をするために弁護士を活用しよう」という発想が生まれます。
「何かコトが起きた時に弁護士に相談する」のではなく、「何かコトが起きないように弁護士を活用する」のです。
経営者は、顧問弁護士と定期的に話すことでリスクを回避し、安心して経営に集中できる
そんな中で役に立つのが、顧問弁護士です。
顧問弁護士を雇い、2ヶ月に一度であっても定期的に弁護士と話す機会を持つことをお勧めします。
具体的には
・自社が今どんな状況にあるのか
・何をしようとしているのか
について
・事業そのもの
・従業員
・取引先の動き
の面から話をするのです。
もしその中で、法律に絡むことがあれば弁護士が必ず指摘してくれますし、「こうすべきですよ」というアドバイスをしてくれます。
何か問題が起きた初期に、弁護士からの適切なアドバイスがあれば、大きな問題となることを防げますから、経営者は安心してご自分のすべきことに集中できますよね。

いかがでしたでしょうか。
各士業の「大まかな違い」と、「活用できる業務や領域」についてご理解いただけましたでしょうか。
当会は「中小企業に顧問弁護士を無料紹介する」組織ですので、4.弁護士(特に顧問弁護士)についての記述がメインになりましたが、各士業の違いをご理解いただいた上で、彼らを賢く活用したいものですね。
(了)
\関連記事:ぜひお読みください! /
顧問弁護士紹介コーディネーターブログ&当会のご案内
\中小企業経営者の顧問弁護士選びのお手伝い!/
中小企業専門の顧問弁護士紹介15年。
まずはお気軽にお電話でご相談ください。tel.03-6679-2076
貴社のご要望やご不安を丁寧にヒアリングし、最適な弁護士をご紹介。もちろん、メールフォームからもお申込み可能です。
安心して経営に集中できる未来を、一緒に目指しませんか。

コーディネーター歴15年の中川です。
経営者の困りごとやご不安を受けとめます!
お話は予めまとめて弁護士に伝えますので、弁護士面談に安心して臨んでいただけます。
webフォームでの顧問弁護士無料紹介申込み
\弁護士全員が顧問料1万円/